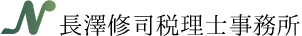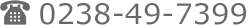臨機応変に対応する
みなさんこんにちは![]()
毎日暑いですね…もう溶けそうです![]()
先日会合で設備関係の仕事をしている方とお話しする機会があり、「エアコン設置など大変でないですか?」![]() と聞いたところ、「エアコン設置する人たちが熱中症で倒れて大変だ」
と聞いたところ、「エアコン設置する人たちが熱中症で倒れて大変だ」![]() とのことでした
とのことでした![]()
エアコンを設置する部屋は普通に考えてエアコンがついてないでしょうから、ものすごく暑い空間や外で仕事をしているのだと思います![]()
私は、高校卒業してからずっとこの仕事しかしていないので、寒暖などで大変な思いをしたこと自体あまりありません![]()
しかし、そういった人がいるからこうして涼しいところで仕事ができていることを忘れてはいけませんね![]()
![]()
さて今回は、松下幸之助著「人を活かす経営」より、<臨機応変に対処する>をお送りします。
米沢で最も有名といってもいい上杉謙信のお話となります。
お互い人間は、規則とか決まりというものをよくつくる。
つくって、それをお互いに守りあおうとする。
これは大切なことで、お互いが決まりを守ってこそよき秩序が保てるのである。
そして秩序が保たれていてこそ、お互いがそれぞれの活動をスムーズに進めることができる。
だから、そこによりよき成果があがって、みんなの生活が向上することにつながる。みんなのための規則であり、決まりなのである。
それはそれでいいけども、しかし、その決まりや規則を守ることのみにとらわれてしまうと、これははたして好ましいかどうか。
その点を、ときにお互いに振り返ってみる必要がないだろうか。
上杉謙信といえば、川中島で武田信玄と一騎打ちをしたという有名な戦国武将であるが、その上杉謙信にこんな話があるという。
すなわち謙信は毘沙門天という神を信仰していた。
七福神の中にも入っている神で、この神は悪魔の軍を降伏させて仏法を守護する神だという。
謙信はこの神を信仰していたので、旗印には毘沙門天の“毘”の字を使っていた。
“毘”の字の旗をひるがえした上杉の軍勢の行くところ、向かうところ敵なしといえるような強さを誇っていたのである。
また、毘沙門天を信仰していたので、何か大事な誓いとか約束などをする場合には、みんなで毘沙門堂に集まった。
そして上座へ謙信がすわり、家老はじめ家中の人々がそこにズラリと並んで座った。
そういうような形の中で、厳粛かつ真剣に誓いをたてたり、約束事をしたわけである。
だから、そうした場所での誓いや約束は、おのずと権威もあり、互いにこれを固く守ったことであろう。
ところが、あるとき隣国に一揆がおこった。
農民たちが領主に反抗して決起したのである。これは大事件である。
うっかりすると、上杉の領内にも及んでくるかもわからない。そうなっては大変である。
しかし、それにどう対応するかということは、一揆の規模とかその状況を実際に見てつかまないことには何とも決められない。
そこで謙信は、隣国へ間者を急いで派遣することにした。
いってみれば、情報収集のための調査員を急行させるというわけである。
しかし、派遣するといっても、当時の隣国といえば、全く別の世界である。
間者ということが知られたら、とらえられて、殺されるのがいわばふつうの姿である。
だから、調査員も命がけである。戦いに行くのと変わらない。
そこで、この間者を派遣するに際して、神文をさせた。
つまり、神の前で誓いをたてた文を読み上げるのである。
家来のものが言った。
「それではさっそく、いつものように、毘沙門堂へ行って、毘沙門天の前で神文をさせましょう。」
これに対して、謙信はこたえた。
「いやいや、今はそんなことをしている暇はない。事は急を要するのだ。いつ一揆がこちらへおしよせてくるかもわからない。すぐにその状況をつかまないといけなのだ。今から毘沙門堂へ連れていったのでは、それだけ遅くなってしまう。もう毘沙門堂へは行かなくてよい。私の前で神文させよ」
家来たちはおどろいた。こんなことは今までになかった。
とくに、長い間のしきたりに慣れている老臣たちは、これはおかしい、これはいつもの決まりに反する、ということで、ブツブツ言った。
その姿を見て、謙信はどうしたか。別に腹も立てない。ニッコリ笑って次のように言ったのである。
「考えてもみよ。私があるから毘沙門天が用いられるのだ。私が信仰しているから、毘沙門天が使われてるのだ。もしも私がいなければ、別に毘沙門天が使われることはなかったであろう。ほかのどの神だっていいわけだ。だから、私が毘沙門天を二、三度拝んだら、毘沙門天も私を三十度も五十度も拝んでいただいてちょうどいいくらいだ。
だからこの場は、私を毘沙門天と思って、私の前で神文をさせればそれでいいのだ」
これを聞いて、家来たちもやっと納得がいった。
わざわざ毘沙門堂までいかなくても、謙信の前で神文をさせればよい。
ふつうの場合ならともかく、こういう緊急の場合はそれでもよい。
なるほど、わかった、というので、みんなは納得して、間者にその場で神文をさせた、というのである。
(中略)
いずれにしろ、臨機応変ということである。
そして臨機応変が本当にできるためには、やはり、人間が主座を保っていなければできにくいのではなかろうか。
あれはああしなければならない、これはこうでなければならないというように、しきたりや決まりにとらわれていては、臨機応変は難しいのである。
やはり、常に人間が主座を保ち、主体性を保持していて、はじめてそれが可能になる。
我々の日常の仕事にしろ、会社の経営の上においても、また商売の上においても、そういう謙信の態度は、大いに参考とすべきものがありはしないと思うのだが、どうであろうか。
これを最近久しぶりに読んで、「ああ、昔も今も変わらないものだな」と感じてしまいました。
人は年数が経てば経つほど変化に否定的になるのだなと、「前のほうがいいに決まっている」という固定概念がどうしても先行してしまいます。
でも、いつの世も常に変化をしていかなければ時代に取り残されてしまいます。
だから、変化を恐れずに立ち向かっていかなければならないと思います。
自分もだんだんと年齢を重ねるとそうなるのかもしれないと自分を律していきたいと思います。
それではまた! 
家庭と仕事の関係
みなさんこんにちは![]()

突然の画像です
先日寝ようと寝室に上がろうとしたとき階段上でこの状態で固まっているレンがいたので激写しました![]()
「…これ人間でやったら超セクシーじゃん!」と妻に言ったら爆笑でした![]()
皆さんにもぜひお見せしたくて載せました![]()
股間にモザイク必要かなぁ…( ´艸`) ・・・・入れました、一応(笑)
さて、話を戻して、今回は少し昔話を交えたお話をしたいと思います。
甲子園も始まり、いよいよ夏本番ですが、この時期は自分が学生時代の部活である吹奏楽の大会も県大会・東北大会の時期で白熱しておりました。
先日、山形県大会の記事を見てそう言えばと思ったことがありました。
それは、指揮者によって音楽が変わるということです。
本当に不思議なのですが、演奏者は同じでも指揮者が変わると音楽の雰囲気が変わったり、時には音楽のレベルが上がったりします。
技術レベルは同じなのになぜそうなるのだろうかと、指揮はテンポを指示し、音を組み立てたり、調整したりする役割を持つのですが、どうもそれだけではないようです。
良い指揮者とは、それぞれ演奏者が持っている良いところを引き出し、そのひとの能力を最大限に引き出すすべを持っていると思います。
これは、ほかのスポーツ競技や会社の経営に関しても同じことが言えるのではないでしょうか。
とくに会社の経営に関しては、経営者のスタンス次第で会社の状況がガラッと変わるものをよく見ます。
なので、私はお客様の経営指導をする際には、まずは経営者の考え方や行動に関して優先して指導することを心がけています。
経営者の鏡が会社であり、その逆も然りです。
その中でよくあるのですが、その経営者の家庭環境がうまくいっていないとき、まず会社経営もうまくいかない場合があります。
その時は、まず家庭環境の改善に力を注ぎ、それが改善したうえで会社経営の指導をしていきます。
まず2つ同時に行うことは不可能だと思っています。
経営者も人間であり、体は一つです。
悩みがあればそれに体と心は引っ張られます。
なので、まずはその悩みをなくしてから課題に取り組んでもらっています。
どちらも長丁場になる場合がありますが、少しでも悩みが解消すれば仕事に集中してもらえます。
なので、優先すべきは今悩みを抱えている方を最優先します。
私は、人生の優先順位は家庭だと思っています。
仕事のために家庭を犠牲にすることは美談でも何でもありません。
時には犠牲にするときもありますが、かならずそのあとにはフォローをすべきです。
家族の支えがあるから仕事ができていることを忘れてはいけないと思います。
この考え方をぜひ経営者が社員に対しても行ってもらいたいと思います。
社員・経営者の家庭環境が良好であればまず会社経営もうまくいきます。
社員も退職することもなく、会社の不満なども限りなく減少できると思います。
結果として経営がスムーズにいきます。
なかなか難しい局面もあると思います。
しかし、このことを思っているだけでも、その人が持つオーラというか佇みが違ってきます。
余裕も出てきます。
一度実践してみて下さい。
きっとうまくいくことが増えると思います!
なんか前半の話と後半の話がかみ合っていないような感じがしますがすみません! ご了承下さい。
それではまた! 
お盆休みのご案内
2018年8月11日(土)から15日(水)は、
お休みとさせていただきます。
役員報酬について
みなさんこんにちは![]()
毎日暑いですね![]()
ほんとに溶けます![]()
暑いのでビールがおいしく感じてしまい、最近また太り始めてしまいました![]()
9月に自転車のイベントに参加する予定なのですが、何とかその時までに痩せなきゃと思っていますがどうなることやらです![]()
さて、今回は役員等への給与と税務調査(税務通信No.3515より抜粋)をお送りします。
|
法人税の調査では、大半のケースで役員給与が正しく処理されているかチェックされるという。役員給与は法人の利益調整に利用されやすいためだ。この際、「使用人兼務役員」や「使用人兼務役員になれない者」に対する給与等の支給状況等も詳細に確認されるそうだ。
税務上の使用人兼務役員とは、役員(社長、理事長等を除く)のうち例えば、部長、課長、支店長、工場長など「法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」が該当する(法法34 ⑤)。
税務調査では、使用人兼務役員に対する賞与について他の使用人と同時期に支給したものか(使用人としての職務に対するものか)、使用人兼務役員になれない者に対する給与が適切に処理されているか等を中心に確認されるようだ。
この点、監査役(税務上使用人兼務役員になれない者)などの定期同額給与について、12カ月で割り切れない額が勘定科目内訳明細書に記載されていること等を端緒に調査が行われたケースもあるそうだ。定期同額給与は、“支給時期が1カ月以下の一定期間ごとで、かつ、各支給時期における支給額が同額であるもの”を損金算入の要件としており、通常は、「1カ月当たりの支給額×12」が定期同額給与となるためだ。
このケースは、期中に使用人から役員に就任したため12カ月で割り切れない額となっていたようだが、同明細書からはこうした動きが一切わからないため確認が行われたとのこと。
当局側は、役員のなかに期中まで使用人であった者がいる場合は、「××は△月△日から役員に就任したため定期同額給与は△月分からの支給額である」など状況を明らかにする内容(メモ程度)を同明細書の余白に記入して欲しいとしている。 |
実際の調査ではやはり役員報酬は必ず見られます。
定期同額給与の決定時期なども議事録などで必ず確認しますので議事録は完備する必要があります。
それでは、また!
臨時休業のお知らせ
研修会のため
2018年7月30日は、臨時休業
とさせていただきます。